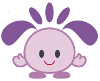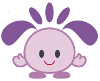


避難場所は我孫子中学校です。(クリックすると地図が出ます)
Wikipedia:ウィキペディア長居より
概要
長居(ながい)は、大阪府大阪市住吉区東部および同市東住吉区西部の地名
である。
現在の住居表示としては、住吉区長居1-4丁目・長居西1-3丁目・長居東1-4丁目、および東住吉区長居公園がある。
住吉区側は住宅地となっていて、一戸建て住宅と団地・マンションが混在している。
東住吉区側についてはほぼ全域が長居公園の敷地となり、公園内に各種施設が設置されている。
2005年度の国勢調査によると、地域の人口は24,279人となっている。
長居の地名は、地域内にあった大御池が「長居池」の通称で呼ばれていたことに由来する。なお、大御池(長居池)は現存しない。
「長居」や「長居陸上競技場」などを、マスコミ報道では「ながい」と「な」にアクセントを置いて発音されるが、正しくは、「ながい」とアクセント無しか、
「ながい」と「が」にアクセントを置く。マスコミ報道でも、「長居公園」や「長居スタジアム」というときは「長居」が正しいアクセントで発音されているの
で、
それに合わせるのが適当である。
歴史
現在の長居地域は、江戸時代には摂津国住吉郡寺岡村・堀村・前堀村の3つ
の村に分かれていた。農村地帯として米や麦、蔬菜などの栽培がおこなわれていた。
寺岡村・前堀村は相模小田原藩領、堀村は下総古河藩領となっていた。
明治時代に入り、1889年の町村制の実施に伴い、寺岡村・堀村・前堀村は周囲の村と合併し、住吉郡依羅(よさみ)村が成立した。
その後1894年には、依羅村から旧寺岡村・堀村・前堀村の地域が分離して、住吉郡(のち東成郡)長居村として独立した。
長居村は1925年に大阪市に編入され、住吉区に属した。旧長居村の地域は、かつての寺岡村の地域(長居村大字寺岡)が「住吉区西長居町」、
かつての堀村の地域(長居村大字堀)が「住吉区東長居町」、かつての前堀村の地域(長居村大字前堀)が「住吉区南長居町」となった。
また1943年には当時の住吉区から阿倍野区・東住吉区を分離したことに伴い、長居公園の予定地は東住吉区の所属となった。
何度かの町名改正を経て、1981年の住吉区全域での住居表示実施により現在の町名となっている。
なお、旧長居村の範囲と、現在「長居」の住居表示となっている地域との間には、若干の範囲の違いがある。
1928年から地域内に長居公園の整備計画が始まった。大阪市が公園予定地の買収などをおこなったが、第二次世界大戦の激化に伴って公園整備計画は一時中
断され、
防空陣地や農場などに転用された。公園は終戦後競馬場・競輪場として一時使用されたのち、1959年から公園整備が再開された。
一帯は第二次世界大戦終戦直後までは農村地帯だったが、1950年代初期頃から宅地開発が進められ、団地や住宅が建ち並ぶ住宅地へと変化した。
沿革
1889年(明治22年)4月1日 -
町村制の施行により、住吉郡依羅村が発足。
1894年(明治27年) - 依羅村の一部(大字寺岡・堀・前堀)が分立して長居村が発足。
1895年(明治28年) - 東成郡長居尋常小学校(現在の大阪市立長居小学校)が開校。
1896年(明治29年)4月1日 - 郡制の施行により、所属郡が東成郡に変更。
1925年(大正14年)4月1日 - 長居村が大阪市に編入。住吉区の一部となる。
1928年(昭和3年) - 長居公園の整備計画が始まる。
1929年(昭和4年)7月18日 - 阪和電気鉄道 臨南寺前駅(現在のJR阪和線長居駅)が開業。
1943年(昭和18年)4月1日 - 住吉区から東住吉区が分区。長居地区のうち長居公園の敷地は東住吉区となる。
1945年(昭和20年) - 成器商業学校(現在の大阪学芸高等学校・附属中学校)が現在地に移転。
1960年(昭和35年)7月1日 - 大阪市営地下鉄1号線(現・御堂筋線)の長居駅が開業。
2006年(平成18年) - 阪和線の高架化工事が完成。